テクノロジー
技術レポート:アーカイブ
Category:カーエレクトロニクス
UMLモデリングによる設計精度の向上
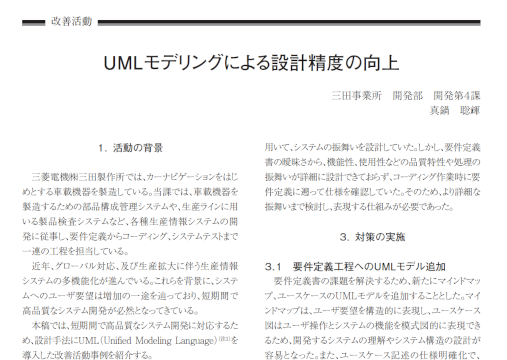
三菱電機(株)三田製作所では、カーナビゲーションをはじめとする車載機器を製造している。当課では、車載機器を製造するための部品構成管理システムや、生産ラインに用いる製品検査システムなど、各種生産情報システムの開発に従事し、要件定義からコーディング、システムテストまで一連の工程を担当している。近年、グローバル対応、及び生産拡大に伴う生産情報システムの多機能化が進んでいる。これらを背景に、システムへのユーザ要望は増加の一途を辿っており、短期間で高品質なシステム開発が必然となってきている。本稿では、短期間で高品質なシステム開発に対応するため、設計手法にUML(Unified Modeling Language)(注1)を導入した改善活動事例を紹介する。
参考情報:
UMLモデリングによる設計精度の向上 1.活動の背景 三菱電機㈱三田製作所では、カーナビゲーションをはじめとする車載機器を製造している。当課では、車載機器を製造するための部品構成管理システムや、生産ラインに用いる製品検査システムなど、各種生産情報システムの開発に従事し、要件定義からコーディング、システムテストまで一連の工程を担当している。近年、グローバル対応、及び生産拡大に伴う生産情報システムの多機能化が進んでいる。これらを背景に、システムへのユーザ要望は増加の一途を辿っており、短期間で高品質なシステム開発が必然となってきている。本稿では、短期間で高品質なシステム開発に対応するため、設計手法にUML(Unified Modeling Language)(注1)を導入した改善活動事例を紹介する。 2.課題の整理 改善活動の手始めとして、開発の工程毎に作業時間を分析した。その結果、全工程に占めるコーディング作業の比率が高いことが判明した。さらに分析を進めた結果、2つの課題が明確となった。2.1 要件定義工程の課題要件定義書は、図表が少なく、文章中心に記載しているため、開発するシステムの構造を把握しづらい。また、曖昧な記述により、設計工程の担当者へ誤認識を誘発させ、誤った設計や設計漏れが発生していた。課題として、ユーザや設計工程の誤認識を防止し、正確にシステム分析を進める対策が必要であった。2.2 設計工程の課題UMLモデルの設計不足が問題であった。設計工程では、クラス図、シーケンス図、アクティビティ図などのUMLモデルを用いて、システムの振舞いを設計していた。しかし、要件定義書の曖昧さから、機能性、使用性などの品質特性や処理の振舞いが詳細に設計できておらず、コーディング作業時に要件定義に遡って仕様を確認していた。そのため、より詳細な振舞いまで検討し、表現する仕組みが必要であった。3.対策の実施3.1 要件定義工程へのUMLモデル追加要件定義書の課題を解決するため、新たにマインドマップ、ユースケースのUMLモデルを追加することとした。マインドマップは、ユーザ要望を構造的に表現し、ユースケース図はユーザ操作とシステムの機能を模式図的に表現できるため、開発するシステムの理解やシステム構造の設計が容易となった。また、ユースケース記述の仕様明確化で、曖昧な記述を排除した。これらの効果で、ユーザや開発担当者の誤認識を防止した。手順は図1に示すように、マインドマップを用いてユーザの思考を展開し、要件そのものの見落しを防止する。次に、マインドマップで収集したユーザ要望の中で、「システム化の範囲」に着目し、マインドマップのユーザ要望のブランチ(枝)に対して、ユースケースを作成する。また、ユースケース記述の作成で、処理の概要に加えて、条件、系列、アクターを定義し、ユーザの操作やシステムの振る舞いを具体化する。さらに、マインドマップとユースケース図/ユースケース記述を連携させることで、ユーザの作業手順とシステム構成の繋がりを強化する。図1.要件定義工程のUMLモデル作成手順UMLモデリングによる設計精度の向上三田事業所 開発部 開発第4課真鍋 聡輝(注1 ) 主にオブジェクト指向分析や設計のための、記法の統一がはかられたモデリング言語である。72UMLモデリングによる設計精度の向上改善活動3.2 設計工程の手法改善設計工程の課題を解決するため、要件定義で具体化したユースケースに基づいて、システム分析と設計の詳細化をUMLモデルを用いて進めた。これにより、ユーザ要望に即した詳細な振舞いの検討が可能となり、設計誤りや設計漏れを防止した。手順は、図2に示すように、クラス図を作成する。作成にあたっては、ユースケースの取扱う情報や操作、それに対する機能を分析、システムの構造を用いて詳細化する。次に、シーケンス図で、処理の流れを設計する。さらに、詳細処理を、アクティビティ図で作成する。シーケンス図とアクティビティ図では、ユースケース記述の処理概要、条件、系列、アクターを用いて、品質特性や処理の振舞いを詳細に記載する。クラス図やシーケンス図、及びアクティビティ図は、プログラムの構造が明らかになるまで、詳細化を進める。この様に、上流工程からUMLモデルを中心に設計の詳細化を進めることで、設計精度を向上した。図2.設計工程のUMLモデル作成手順3.3 UMLモデルの共有要件定義、設計工程に新たなUMLモデルを追加したことで、モデルの作成時間が増加した。そこで、モデル作成の時間短縮を目的に、共同作業の環境を整備した。従来、担当者が個別に管理していたモデルを構成管理ツールで管理し、担当者間でリアルタイムに共有し、モデル作成を効率化した。4.効果の確認対策を適用したシステム開発プロジェクトについて、工程毎の作業工数を記録し、従来型の開発を行った場合の試算値と比較した。結果、図3に示すように、要件定義、設計の工数が増加した半面、詳細設計とコーディングに要する工数が約40%減少、総工数として約7%削減した。また、フロントローディング化率では、従来の開発に比べて13%改善し、86%となり、生産性と設計精度の向上を確認した。図3.開発工数の計測結果5.今後の課題現在、新たな取組みとして、アジャイル開発を実施している。理由は、開発期間が2週間程度で区切られ、仕様変更が多い場合でも、開発の区切りごとで追加対応できる特徴にある。今後の課題として、アジャイル開発に、今回改善したUMLモデルの適用、及び新たなUMLモデルの活用を検討し、継続的な設計精度の向上に取り組む。6.むすび今回の活動により、UMLモデルを軸とした設計手法を確立し、システム開発の生産性と設計品質を向上することができ、課員の設計力向上も期待できる。最後に、本活動にあたり多くの助力をいただいた関係者各位に深く感謝申し上げる。執筆者紹介真鍋 聡輝 マナベ トシキ2016年入社。主に社内生産システムのソフトウェア開発に従事。現在、三田事業所開発部開発第4課。73UMLモデリングによる設計精度の向上