テクノロジー
技術レポート:アーカイブ
Category:社会インフラシステム
ソフトウェア設計力強化活動の改善
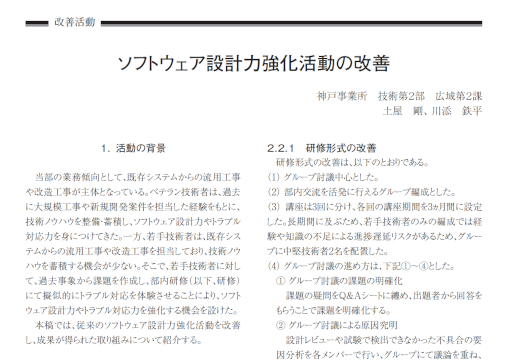
当部の業務傾向として、既存システムからの流用工事や改造工事が主体となっている。ベテラン技術者は、過去に大規模工事や新規開発案件を担当した経験をもとに、技術ノウハウを整備・蓄積し、ソフトウェア設計力やトラブル対応力を身につけてきた。一方、若手技術者は、既存システムからの流用工事や改造工事を担当しており、技術ノウハウを蓄積する機会が少ない。そこで、若手技術者に対して、過去事象から課題を作成し、部内研修(以下、研修)にて擬似的にトラブル対応を体験させることにより、ソフトウェア設計力やトラブル対応力を強化する機会を設けた。本稿では、従来のソフトウェア設計力強化活動を改善し、成果が得られた取り組みについて紹介する。
参考情報:
- この技術レポートは、当社が展開する公共・エネルギー事業の社会インフラシステムソリューションに係る技術について著述されたものです。
- 社会インフラシステムソリューションは、神戸事業所が提供しています。
ソフトウェア設計力強化活動の改善 1.活動の背景 当部の業務傾向として、既存システムからの流用工事や改造工事が主体となっている。ベテラン技術者は、過去に大規模工事や新規開発案件を担当した経験をもとに、技術ノウハウを整備・蓄積し、ソフトウェア設計力やトラブル対応力を身につけてきた。一方、若手技術者は、既存システムからの流用工事や改造工事を担当しており、技術ノウハウを蓄積する機会が少ない。そこで、若手技術者に対して、過去事象から課題を作成し、部内研修(以下、研修)にて擬似的にトラブル対応を体験させることにより、ソフトウェア設計力やトラブル対応力を強化する機会を設けた。本稿では、従来のソフトウェア設計力強化活動を改善し、成果が得られた取り組みについて紹介する。 2.活動内容 当部では、ソフトウェア設計力(以下、設計力)の強化活動として、従来は講座形式の研修を中心に実施してきたが、背景で述べた業務傾向に対応した活動を早急に確立する必要があった。2.1 従来の活動における問題点従来のソフトウェア設計力強化活動の問題点は、以下のとおりである。( 1) 書籍に沿った講座形式の為、研修のポイントが身近に感じられず、充分な成果が得られ難い。(2) 講座形式の為、受講生が受け身となりやすい。( 3) 短期間の研修の為、受講生自らの考えを表現する時間が取れず、若手技術者間で話す機会も少ない。2.2 今回の改善活動従来のソフトウェア設計力強化活動の問題点から研修形式、研修内容の改善策を取込み、活動内容を大幅に変更した。個別にポイントを説明する。2.2.1 研修形式の改善研修形式の改善は、以下のとおりである。(1) グループ討議中心とした。(2) 部内交流を活発に行えるグループ編成とした。(3) 講座は3回に分け、各回の講座期間を3ヵ月間に設定した。長期間に及ぶため、若手技術者のみの編成では経験や知識の不足による進捗遅延リスクがあるため、グループに中堅技術者2名を配置した。(4) グループ討議の進め方は、下記①~④とした。① グループ討議の課題の明確化 課題の疑問をQ&Aシートに纏め、出題者から回答をもらうことで課題を明確化する。② グループ討議による原因究明 設計レビューや試験で検出できなかった不具合の要因分析を各メンバーで行い、グループにて議論を重ね、課題の原因を究明する。③ 対策案に関する議論 若手技術者は、市販書籍やインターネットでの調査、類似システムのソフトウェア設計書の調査やベテラン技術者への聞き取りを行い、対策案を持ち寄り、議論することで活性化を図る。④ 報告会 グループ討議での検討結果を整理する目的で報告会資料を作成する。報告会(図1参照)には、メンバーに加え聴講者として上長、ベテラン技術者を参加させることにより、多角的な視点からの活発な質疑応答や意見交換を図る。図1.報告会ソフトウェア設計力強化活動の改善神戸事業所 技術第2部 広域第2課土屋 剛、 川添 鉄平70ソフトウェア設計力強化活動の改善改善活動2.2.2 研修内容の改善研修内容に対する改善は、以下のとおりである。(1) 研修課題の選定ベテラン技術者が過去事例集から技術伝承を目的とし、以下の観点で研修課題を選定した。① 制御におけるシーケンス処理の設計② システムの二重系切替におけるソフトウェア設計③ エラー処理設計、保守性を考慮した設計等(2) 擬似体験研修研修課題の説明は、敢えて簡易なものとし、若手技術者が自ら設計上の問題点、その解決策を考える形とし、正解を導き出す過程を擬似的に体験させるようにした。(3) 研修課題例図2に「制御におけるシーケンス処理の設計」の課題例を示す。本事象は、シーケンス崩れにより制御に失敗した事例である。具体的には「制御管理プロセス」と「状態管理プロセス」間の同期処理の不備が、状態不整合を発生させる原因の一つである。状態不整合の発生要因を自ら気づかせ、その解決策を考えさせることを狙いとしている。図2.研修課題例3.活動成果活動成果は、以下のとおりである。(1) 組織的成果本改善により、技術伝承の為の研修の仕組みを確立できた。また、技術ノウハウの共有や、若手技術者の実力を詳細に把握することにより、今後の技術者育成への重要なヒントを得られた。(2) 若手技術者における成果若手技術者が自ら考える機会を得られた。また、ソフトウェア設計に必要な知識や実現方式を議論し、報告会での的確なアドバイスにより、若手技術者は新たな気付きを得ると共に、設計力向上、加えてプレゼンテーション能力が向上した。(3) 付随成果本活動の付随成果として、メンバーからは以下の積極的な所感が寄せられ、今後のソフトウェア設計業務へのモチベーションアップに繋げることができた。何より、若手技術者が「自分達で考え、修得できた」ことによる達成感を得られたことがマインドアップに繋がった。① ベテラン技術者の意見を聞くことで、理解を深めることができた。② 自らの設計に対して、経験に裏付けられた技術者の意見を聴くことが重要と感じた。③ 部内メンバーと活動したことで視野が広がった。4.むすび今回の活動として、設計力強化に効果があったが、設計力強化すべき項目の全てを満足するまでには至っていない。今後はリソース管理、処理性能等の項目に対して、継続して活動していく。最後に、本活動を支援いただいた、関係者各位に深く感謝申し上げる。執筆者紹介土屋 剛 ツチヤ タケシ1992年入社。主に遠方監視制御システムのソフトウェア開発に従事。現在、神戸事業所技術第2部広域第2課。川添 鉄平 カワゾエ テッペイ1998年入社。主に遠方監視制御システムのソフトウェア開発に従事。現在、神戸事業所技術第2部広域第2課。71ソフトウェア設計力強化活動の改善