テクノロジー
技術レポート:アーカイブ
Category:情報処理システム
EVM(Earned Value Management)の基礎
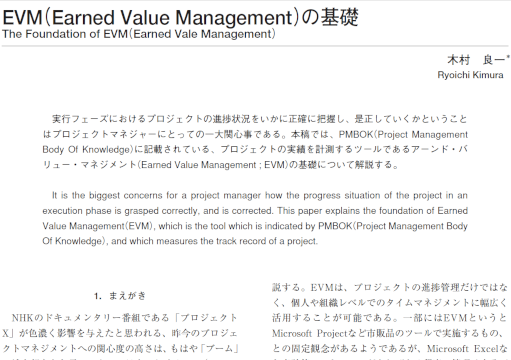
実行フェーズにおけるプロジェクトの進捗状況をいかに正確に把握し、是正していくかということは、プロジェクトマネジャーにとっての一大関心事である。本稿では、PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)に記載されている、プロジェクトの実績を計測するツールであるアーンド・バリュー・マネジメント(Earned Value Management; EVM)の基礎について解説する。
参考情報:
EVM(Earned Value Management)の基礎 *鎌倉事業部 第四技術部 MSS技報・Vol.17 32EVM(Earned Value Management)の基礎The Foundation of EVM(Earned Vale Management)木村 良一*Ryoichi Kimura 実行フェーズにおけるプロジェクトの進捗状況をいかに正確に把握し、是正していくかということはプロジェクトマネジャーにとっての一大関心事である。本稿では、PMBOK(Project ManagementBody Of Knowledge)に記載されている、プロジェクトの実績を計測するツールであるアーンド・バリュー・マネジメント(Earned Value Management ; EVM)の基礎について解説する。 It is the biggest concerns for a project manager how the progress situation of the project in anexecution phase is grasped correctly, and is corrected. This paper explains the foundation of EarnedValue Managemen(t EVM), which is the tool which is indicated by PMBOK(Project Management BodyOf Knowledge), and which measures the track record of a project. 1.まえがき NHKのドキュメンタリー番組である「プロジェクトX」が色濃く影響を与えたと思われる、昨今のプロジェクトマネジメントへの関心度の高さは、もはや「ブーム」の域を超えたと言ってよい。日本におけるPMP(ProjectManagement Professional)の資格取得者は、9,000名を超えており、この数字は、米国、カナダについで第三位の位置を占めている。急速な発展を遂げているアジア諸国の厳しい追い上げがあるものの、景気がそれほど上向いていないわが国の状況下においては先にあげたプロジェクトマネジメントへの関心度の高さを裏打ちするものであろう。しかし、その関心度の高さとは裏腹に、どの開発の現場においてもいまだ大きな変化は起こっていないように見受けられる。その原因は各プロジェクトによって様々であると思うが、ひとつには、各プロジェクトメンバーの「プロジェクト管理はプロジェクトマネジャーがやるもの」という固定観念に根ざすところがあるのではないだろうか。プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトマネジャーとプロジェクトメンバーが協働することが必要であり、プロジェクトメンバー全員がプロジェクト管理の必要性、有用性について理解しておくことが望ましい。本稿では、プロジェクトマネジメントにおける、プロジェクトの進捗管理のツールとしてもはやスタンダードとなりつつあるEVMについて、その考え方の基礎を概説する。EVMは、プロジェクトの進捗管理だけではなく、個人や組織レベルでのタイムマネジメントに幅広く活用することが可能である。一部にはEVMというとMicrosoft Projectなど市販品のツールで実施するもの、との固定観念があるようであるが、Microsoft Excelなど表計算ソフトウエアがあればある程度の管理は十分可能である。 2.EVMの歴史概観 米国では1993年、膨大な国家赤字を見直すべくクリントン・アドミニストレーションが発動されたが、その際、国防省(DoD;Department of Defense)においてもプロジェクトのパフォーマンス測定や報告手法が見直され、調達規格が改訂された。これがEVMの誕生である。1998年6月にはANSI/EIA #748-98「アーンドバリュー・マネジメントシステムに対する産業界のガイドライン」が公開され、政府調達のプロジェクトの前提条件となっている。わが国においても2003年に経済産業省・情報処理振興事業協会により「EVM活用型プロジェクトマネジメント導入ガイドライン※1」が公開されるなど、EVM導入の動きが活発であり、今後は各省庁がシステム調達時に、ITベンダーに対してEVMによる進捗管理を要求するケースは確実に増えると考えられる。これを受け、EVMを導入している企業が着実に増えてきている。※1 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/evmguideline.pdf333.従来の進捗管理ソフトウエア開発はビル建設のように、その進捗具合を実際に目で見ることができない。したがって、進捗の管理をしようとすると、目に見えるようにする工夫が必要である。従来実施していた管理手法のひとつとして、プロジェクトマネジャーが会議などで各メンバーに進捗の度合いをヒアリングし、工程表上の線を塗りつぶすなどして進捗を把握できるようにする、という手法がある。この方法では、進捗の度合いが定性的で各メンバーの感覚に支配されており、順調に進んでいたはずの進捗が、完了直前に90%で止まってしまうといった、いわゆる「90%症候群」が発症してしまう可能性がある。これでは、進捗の度合いを定量的に測ることは困難である。もうひとつの手法として、メンバーごとに実施すべき作業総数のうち、いくつ完了したかをヒアリングするものがある。これにより、全体の作業量のうち大体何パーセントが終了しているか、このペースで行けばいつごろ終わるか、を予測することができる。これは割とよく使用されている手法である。しかしこの手法には工数の概念が入っていない。そのため、進捗どおり進んでいるように見えても、実際その作業にどのくらいの工数を消費しているか把握することができない。これらの進捗管理手法において不足していた点を解消し、プロジェクトの進捗状況を定量的に評価・分析するツールがEVMである。4.EVMを活用した進捗管理4.1 指標の算出EVMで使用する基本指標を表1に示す※2。EVMにおいてすべての分析の成否はこの四つ(特に出来高、計画値、実績の三つ)の基本指標をいかに正確に収集できるかにかかっているといっても過言ではない。これらの基本指標を用いて、表2に示す分析指標を算出する。以下に、いくつかの分析指標の説明を示す。盧スケジュール差異(SV)スケジュール差異が正の場合、プロジェクトは計画より進んでいる。負の場合、プロジェクトは計画より遅れている。※2 この先、目新しい用語が幾つか出てくる。これらの一見難解に見える用語群がEVMの普及を阻んでいると筆者は考えるが、少し我慢して読み進めていただきたい。後述のケーススタディと照らし合わせていただければ、各々の指標の持つ意味が理解いただけると思う。表1 EVMで使用する基本指標※3略 語名 称内 容EVEarned Value:出来高現時点までに完了した作業の工数PVPlanned Value:計画値現時点までの計画工数ACActual Cost:実績値現時点までに実際にかかった工数BACBudget At Completion:計画総工数プロジェクト完了までに割り当てられた計画上の総工数略 語名 称内 容SVSchedule Variance:スケジュール差異現時点での出来高(EV)と計画値(PV)の差CVCost Variance:コスト差異現時点での出来高(EV)と実績値(AC)の差SPISchedule Performance Index:スケジュール効率指標出来高(EV)と計画値(PV)の比率VACVariance At Completion:完了時コスト差異計画した総工数(BAC)と現時点で見積もったプロジェクト完了時の予測総工数(EAC)の差CPICost Performance Index:コスト効率指標出来高(EV)と実績値(AC)の比率EACEstimate At Completion:完了時コスト予測現時点で見積もったプロジェクト完了時の総工数の予測値式EV-PVEV-ACEV/PVEV/ACAC+(BAC-EV)/CPIBAC-EACETCEstimate To Complete:残作業コスト予測EAC-AC現時点からプロジェクトが完了するまでに必要となる工数表2 EVMで使用する分析指標※3 EV,PV,ACは1965年度版のPMBOKの「EVMS」の解説ではそれぞれBCWP(Budget Cost of WorkPerformed),BCWS(Budget Cost of Work Scheduled)及びACWP(Actual Cost of Work Performed)と解説されていたが、2000年版において「EVM」となった(この際同時に、システムではなくツールであると判断された)際に現在の略語に統一された。一部の書籍においてはいまだ古い表記を使用しているものもあるので注意が必要である。MSS技報・Vol.17 34盪コスト差異(CV)コスト差異が正の場合、プロジェクトは計画した工数内で進んでいる。負の場合、プロジェクトは計画した工数を超過している。蘯スケジュール効率指数(SPI)スケジュール効率指数が正の場合、プロジェクトの進捗率は計画より高い。負の場合、プロジェクトの進捗率は計画より低い。盻コスト効率指数(CPI)コスト効率指数が正の場合、プロジェクトの生産性は計画より高い。負の場合、プロジェクトの生産性は計画より低い。眈完了時コスト差異(VAC)完了時コスト差異が正の場合、プロジェクトは計画工数内で完了する。負の場合、プロジェクトは計画工数を超えて完了する。実際のプロジェクトにおいては、プロジェクトマネジャーは、これらの指標を個々にではなく、全体的に見て状況を評価・分析し、対応策を立てなくてはならない。4.2 分析指標の評価(ケーススタディによる評価例)プロジェクトの進捗状況を把握し、対策を立てるためには、個々の分析指標を定期的に収集し、全ての分析指標を全体的に分析・評価することが必要である。プロジェクトマネジャーとしてのスキルはこれらの分析指標からプロジェクトの現状を把握し、問題発生の兆候を読み取り、どのような対策を立てるかによる。ケーススタディとして表3にあるプロジェクトの7月時点での状況を示す。評価手段の一例としてトレンドグラフとブルズアイチャートを紹介する。これはプロジェクトの状況を見えるようにし、評価しやすくするためのひとつの手段の例であり、必ず実施しなくてはならないというものではない。個々のプロジェクトあるいはプロジェクトマネジャーによっていろいろ工夫の余地がある。盧トレンドグラフプロジェクトの立ち上げ時の計画値(PV)とプロジェクト実施中に定期的に出来高(EV)、実績値(AC)を時系列的にグラフにしたものがトレンドグラフである。トレンドグラフの例を図1に示す。このグラフによりプロジェクトが現在どのような状況にあり、この先どういった傾向にあるかを評価することができる。盪ブルズアイチャート※4定期的に収集した基本指標を元に算出したスケジュール効率指標(SPI)とコスト効率指標(CPI)を分散図として表したものである。ブルズアイチャートの例を図2に示す。プロジェクトマネジャーは、指標ポイントが常に右上の象限で安定するように気をつけておく必要がある。ポイントとしては、計画段階において管理指標(=スケジュール効率指数(SPI)×コスト効率指数(CPI))を定めておき、指標ポイントが管理指標から外れた際に是正を実施することを決めておく。このケースでは、これらのグラフにより以下の状況を見て取ることができる。・出来高(EV)<計画値(PV)となっており、現時点でスケジュールが計画に比べて遅れている。またスケジュール効率指数が1以下であるため、スケジュールが徐々に0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PVACEV図1 トレンドグラフの例計画値(PV)実績値(AC)出来高(EV)スケジュール効率指数(SPI)コスト効率指数(CPI)1月10 10 8 0.80 0.802月15 17 12 0.80 0.713月20 25 16 0.80 0.644月25 35 20 0.80 0.575月35 42 25 0.71 0.606月50 65 35 0.70 0.547月70 80 45 0.64 0.568月909月10010月11011月115表3 あるプロジェクトにおける分析指標0.511.50.5 1 1.5スケジュール効率指標(SPI)コスト効率指標(CPI)図2 ブルズアイチャートの例※4 分散図の形状がブルドッグの目に似ているところからつけられたものと思われるが、命名の所以は定かではない。35遅れていく傾向にある。・出来高(EV)<実績値(AC)となっており、現時点で計画工数を超過している。またコスト効率指数が1以下であり、工数が徐々に超過していき、計画よりも超過してプロジェクトが完了する可能性がある。この状況になるに至った、想定される原因としては、最初の計画段階で、各担当者への割当作業量を多く見積もった、または計画に見合うだけの人員を割り当てていない、などが考えられる。このプロジェクトの進捗を挽回するためにプロジェクトマネジャーが取る是正策は、技術者に対して教育を行う、あるいは人員をスキルの高い技術者と交代する、などが挙げられる。あるいはもともとの計画をみなおし、スケジュールの変更も検討する必要があるかもしれない。スケジュールの延長や技術者の追加投入などの対策を立てる場合は、さらなるコスト超過を覚悟しなくてはならない。このケーススタディの例は単純なケースであるが、実際のプロジェクトにおいても同様に、これらの分析指標を算出し、評価することによりプロジェクトの進捗状況を把握し、プロジェクトの抱えている問題を明確にし、対応策を検討・実施することができる。5.EVMのメリット進捗管理のツールにEVMを採用した場合のそれぞれの立場による様々なメリットの代表的なものを以下に示した。盧組織管理としてのメリットア 現在のプロジェクトの工数状況を含めた進捗状況が定量的に把握できる。イ すべてのプロジェクトに共通の指標を用い、要注意プロジェクトが発見しやすい。ウ プロジェクトマネジャーがとった対応策の妥当性を定量的に評価できる。エ すべてのプロジェクトの指標をまとめ、組織の指標として評価することができる。盪プロジェクトマネジャーとしてのメリットア 現在のプロジェクトの工数状況を含めた進捗状況が定量的に把握できる。イ プロジェクトの進捗状況と計画との差異が明示的に把握できる。ウ 現在のパフォーマンスによるプロジェクトの完了見込み、総工数が推測できる。エ 傾向分析などにより、プロジェクトが抱える問題、改善点を明確にできる。オ 対応策の実施による成果を確認することができる。蘯プロジェクトメンバーとしてのメリットア アサインされた業務の進捗状況を定量的に把握することができる。イ 自分の進捗状況が分かることにより、モチベーションが維持できる。ウ 自分の作業ペースが把握でき、作業計画の精度を向上することができる。エ 過去の作業ペースと比較し、スキルアップを定量的に把握することができる。前にも述べたが、ソフトウエア開発は目に見えることができない。EVMを用いることにより「見える化」することで、各ステークホルダーに様々なメリットを与えることが可能となる。6.今後の課題確かにEVMは使えるツールではあるが、課題がないわけではない。最も大きな問題は「品質」に関するものであろう。EVMはQCDにおけるC(コスト)とD(スケジュール)を把握することができるが、Q(品質)については考慮されていない。いかに進捗が良くても品質が低くては問題があるため、今後EVMにいかに品質を盛り込んでいくか、が課題になると思われる。※5また、EVMはプロジェクト全体を対象とするため、さまざまなタスクが錯綜するような比較的大きなプロジェクトにおけるクリティカルパスを管理することはできない。この点については、クリティカルパスのみを別に取り出すことにより管理することができそうである。7.むすびプロジェクトマネジメント技術におけるEVMの基礎について、プロジェクトメンバーにも分かるように概説したつもりである。EVMを既に実践で活用している方には物足りなかったかもしれないが、再確認の意味で読んでいただきたい。最初から完璧を目指すとなかなか導入は難しい。プロジェクトメンバーにより、EVMのようなツールの基礎を自ら理解し、身近なところから段階的にEVMを導入していただき、それが最終的にはボトムアップによるプロジェクトの「カイゼン」に結びつけば幸いである。また、それに向けて筆者もできうる限りの支援をさせていただきたいと考えている。※5 米国の学会などで品質を考慮に入れたEVMについての研究が実施され始めているようであるが、わが国ではまだそこまでは至っていない。MSS技報・Vol.17 36参考資料盧プロジェクトマネジメントの基礎知識体系ガイド(Project Management Institute)盪アーンド・バリューによるプロジェクトマネジメント(Quentin W. Fleming/Joel M. Koppelman、PMI東京支部)蘯国際標準プロジェクトマネジメント PMBOKとEVMS(能澤 徹、日科技連)盻アドバンスト・プロジェクトマネジメント(能澤 徹、日科技連)眈EVMを極める(日経ITプロフェッショナル2004年12月号特集1)眇EVM活用のメリット(マイクロソフトプロジェクトユーザーズフォーラム(MPUF)EVM研究会資料)眄EVM活用型プロジェクトマネジメント導入ガイドライン(経済産業省・情報処理振興事業協会)